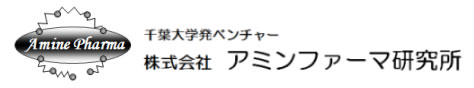アクロレインの可能性
脳梗塞リスク評価マーカーとしてのアクロレインの可能性
(1)酸化ストレスの主役は活性酸素ではなくアクロレイン
ポリアミンは細胞増殖因子であるため、細胞培養系の培地によく添加されます。しかし、牛血清が同時に存在すると牛血清アミンオキシターゼによりH2O2とアクロレインが産生され、細胞増殖が阻害されることがわかりました(図1)。
 (図1)
(図1)
この細胞増殖阻害がH2O2によるのかアクロレインによるのか決定するために、培地中にH2O2を分解するカタラーゼ(Cat)又はアルデヒドを分解するアルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)を添加したところ、ALDH添加時にのみ細胞増殖は回復し、毒性物質はアクロレインであることが明らかとなりました(図2)3)。
 (図2)
(図2)
実際に細胞増殖を阻害するH2O2とアクロレインの濃度を検討したところ、それぞれ0.4 mM と15μM でした(図3(A)、(B)) 3)。
 (図3)
(図3)
これまで同じ酸化ストレスでも、活性酸素に比べ影の薄かったアクロレインが非常に強い細胞毒性を示していることが明らかとなりました。
(2)脳梗塞患者の血中PAO及びアクロレイン量
さらに、脳梗塞とPAO、アクロレイン量の間に相関が認められるか検討しました4)。アクロレインは、スペルミンからスペルミンオキシターゼ(SMO)により合成される3−アミノプロパナール(図1)から生じる以外に、アセチルポリアミンオキシターゼ(AcPAO)により合成される3−アセタミドプロパナールからも少量生じます。この両酵素活性を加えたトータル・ポリアミンオキシターゼ(Total PAO)活性は脳梗塞患者の血漿中で有意に増加していました(図4(A))。
 (図4)
(図4)
さらに、蛋白質結合型アクロレイン(FDP-Lys)量も有意に増加していました。次に発症後40日までの患者の各指標の経時変化を調べたところ、最初にAcPAO活性が上昇し、続いてSMO活性、最後にFDP-Lys量が上昇することが明らかとなりました(図4(B))。AcPAO活性は脳梗塞発症後直ちに上昇するので、発症直後の患者のAcPAO活性とMRIを同時に測定したところ、AcPAO活性の上昇はMRI による梗塞像の検出よりも早い事が明らかとなりました。
(3)脳梗塞リスク=“かくれ脳梗塞” と 血中PAO及びアクロレイン量
統計によると、小さい脳梗塞が検出された人が脳梗塞を発病する確率は健常人に比べ13.1倍高いといわれています)。もし、脳梗塞を無症候のうちに(発症前に)予防することができれば、脳梗塞によるQOLの低下、介護者の負担を軽減することができると考えられます。
これまでに、手足のしびれ等自覚症状があり、MRIで梗塞が検出された11名のTotal PAO活性及びFDP-Lys量は、健常人に比べて有意に高いことがわかっています4)。このほかに、自覚症状はないがTotal PAO活性とFDP-Lys量が高い8名の健常人のMRI測定を行ったところ、4名に梗塞、2名に萎縮が認められました(図5)。
 (図5)
(図5)
脳梗塞リスクマーカーとしてのアクロレインの可能性に期待が高まりました。
(1)酸化ストレスの主役は活性酸素ではなくアクロレイン
ポリアミンは細胞増殖因子であるため、細胞培養系の培地によく添加されます。しかし、牛血清が同時に存在すると牛血清アミンオキシターゼによりH2O2とアクロレインが産生され、細胞増殖が阻害されることがわかりました(図1)。
 (図1)
(図1)この細胞増殖阻害がH2O2によるのかアクロレインによるのか決定するために、培地中にH2O2を分解するカタラーゼ(Cat)又はアルデヒドを分解するアルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)を添加したところ、ALDH添加時にのみ細胞増殖は回復し、毒性物質はアクロレインであることが明らかとなりました(図2)3)。
 (図2)
(図2)実際に細胞増殖を阻害するH2O2とアクロレインの濃度を検討したところ、それぞれ0.4 mM と15μM でした(図3(A)、(B)) 3)。
 (図3)
(図3)これまで同じ酸化ストレスでも、活性酸素に比べ影の薄かったアクロレインが非常に強い細胞毒性を示していることが明らかとなりました。
(2)脳梗塞患者の血中PAO及びアクロレイン量
さらに、脳梗塞とPAO、アクロレイン量の間に相関が認められるか検討しました4)。アクロレインは、スペルミンからスペルミンオキシターゼ(SMO)により合成される3−アミノプロパナール(図1)から生じる以外に、アセチルポリアミンオキシターゼ(AcPAO)により合成される3−アセタミドプロパナールからも少量生じます。この両酵素活性を加えたトータル・ポリアミンオキシターゼ(Total PAO)活性は脳梗塞患者の血漿中で有意に増加していました(図4(A))。
 (図4)
(図4)さらに、蛋白質結合型アクロレイン(FDP-Lys)量も有意に増加していました。次に発症後40日までの患者の各指標の経時変化を調べたところ、最初にAcPAO活性が上昇し、続いてSMO活性、最後にFDP-Lys量が上昇することが明らかとなりました(図4(B))。AcPAO活性は脳梗塞発症後直ちに上昇するので、発症直後の患者のAcPAO活性とMRIを同時に測定したところ、AcPAO活性の上昇はMRI による梗塞像の検出よりも早い事が明らかとなりました。
(3)脳梗塞リスク=“かくれ脳梗塞” と 血中PAO及びアクロレイン量
統計によると、小さい脳梗塞が検出された人が脳梗塞を発病する確率は健常人に比べ13.1倍高いといわれています)。もし、脳梗塞を無症候のうちに(発症前に)予防することができれば、脳梗塞によるQOLの低下、介護者の負担を軽減することができると考えられます。
これまでに、手足のしびれ等自覚症状があり、MRIで梗塞が検出された11名のTotal PAO活性及びFDP-Lys量は、健常人に比べて有意に高いことがわかっています4)。このほかに、自覚症状はないがTotal PAO活性とFDP-Lys量が高い8名の健常人のMRI測定を行ったところ、4名に梗塞、2名に萎縮が認められました(図5)。
 (図5)
(図5)脳梗塞リスクマーカーとしてのアクロレインの可能性に期待が高まりました。